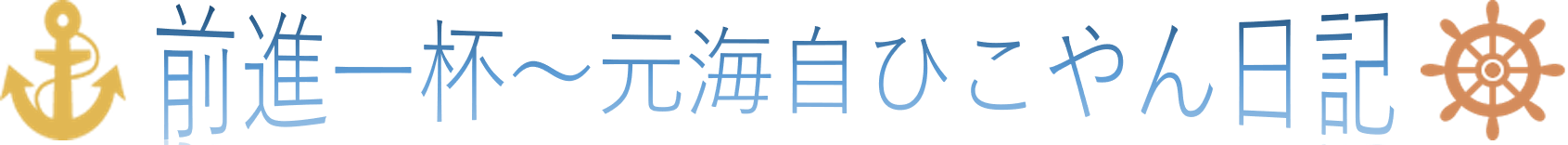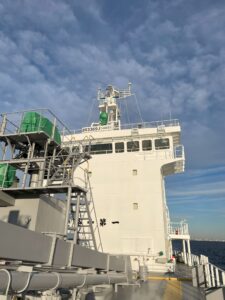現役自衛官の方の中には、民間船に興味を持っている人も数多くいると思います。
しかし、いざそこに踏み込むには、仕事内容、給料、福利厚生、休暇、人間関係…など、
いろいろな面を考えると不安はありますよね。
特に家族がいる方ならなおさらです。
そこで、民間船(749t 6~7人)に転職し2年が経とうとしている私が、ぶっちゃけどうだったのかをお伝えします。
今回は、仕事内容で感じたことや失敗談を書いていきます。
民間船での仕事の内容
自衛艦とは違い、それぞれの配置は少数人数で、一つの作業は基本一人で、一人一人が責任者です。
出入港作業
自衛官時代はブリッジでしか仕事をしていなかったので、オモテの作業は初めてでホーサーをさばくのだけでも慣れないことで、特にウィンドラス操作は、船の態勢を考えながらホーサーを張らないといけないので、最初のうちは一番苦労しました。
サンドレッドは、練習あるのみです!
アンカー編
その時のワッチで入れるので、一人です。
船長からの指示で、コックビル(吊り錨)し、レッコアンカーの令により、アンカーを投入します。
ブレーキ投錨をしますが、最初は自分がブレーキを緩めて出ていくアンカーチェーンの勢いにビックリして慌ててブレーキを閉めてしまったものです。
着底させる前にブレーキをかけると、チェーンに過大な負荷を掛けてしまい最悪切断させてしまいますので、事前に水深を確認して、最低でもその長さは出しましょう!
指揮官も伝令小旗もいないので、繰り出し中ジョイニングシャックル若しくはケンターシャックルを見逃さないように注視する必要があります。
最初のうちは、毎回指示された節数より一つ多く出してました(笑)
慣れないうちは、分かりやすくシャックルに塗装することをおススメします。
岸壁入港編
ブリッジは船長一人で、オモテに甲板部二人、トモに機関部三人が配置につきます。
各人がトランシーバーを持ってますが、主に船長と1航士がマイクでやりとりし、2航士にアンカーやホーサーの指示をします。
ここではオモテの作業の流れをザックリ紹介します。
二人で、岸壁に合わせたホーサーの準備をします。
2航士 1航士からの指示でコックビル(吊り錨)
1航士 岸壁までの距離等を船長に報告
2航士 船長からの指示でアンカー投入
1航士 サンドレッド投てき
2航士 ビットに掛かったらヘッドライン、スプリングを巻く
1航士 船の係留位置を各所に通達
2航士 1航士からの情報からヘッドライン、スプリングを出したり巻いたり調整する
2航士はウィンドラスでヘッドライン、スプリングを一人で操作し、それに加えてアンカーのブレーキ操作でアンカーも状況に応じて出します。
慣れないうちは、1航士の指示どおりやれば大丈夫です、そのうちに、自分で考えてやってみましょう。
出入港を繰り返すたびに上達できるので、私のような初心者でも気づいたらできるようになってたので、大丈夫です。

自衛艦と違いホーサーはウィンドラスに巻かれてあり、準備は繰り出しやすいようにフェアリーダー付近にコイルして準備しておきます。
航海ワッチ
舵、機関、見張り、レーダー、電子海図、国際VHF等、全部一人でやります。
操舵は基本オートパイロットで、船舶のふくそう状況や地理的状況により、手動に切り替えながら行います。
レーダーや電子海図も事故を防ぐために非常な設備なので、操作を覚えておく必要があります。
紙海図はコースによって一応準備し目を通しますが、GPSが正常な限りほとんど使用しません。
国際VHFは、基本的な交話要領は講習で習いますが、内容は相手に伝わりやすいように話すだけなので、自衛艦のような難しい言い回しは必要ありません。
自衛官時代は、堅苦しいハンドブックどおりに話さないといけなかったり、航海指揮官の意図がはっきりわからないままとりあえず他船を呼び出したりと、なにかと緊張したもんでしたが、今は自分の意思を自分のタイミングで伝えることができるので楽勝で、積極的に使用しています。
漁船を除き、他の船舶との衝突を避ける方法は、国際VHFが一番いいと思います。
呼びかけに応じてくれない船もたまにありますけどね( ;∀;)
最初は、船長のワッチにダブルで入るので、安心なのでいろいろ教わりましょう。
ダブルワッチは人によって期間は違いますが、お互いを知ることができたり、他の人のことも知ることができ、人間関係を構築できるいい期間にもなります。
自衛艦では通らない箇所や避航の距離感覚も違うので、毎ワッチが勉強になります。
船側は、早く一人ワッチができるようにと、考えているのでこちらもそれに応えられるよう頑張りましょう!
荷役編
船種によって大きく違いますが、荷役準備は全員で実施し、荷役全般の責任者は1航士です。
本船は荷役中もワッチで回して、バラスト水の注入、排出したり、PC画面で荷役スケジュールに合わせ、各ホールドに振り分けたりしてます。
なにもない限り、PC画面の前で座って監視するだけで、常時なにかしてるわけではないので、体力的には楽です。
整備作業
甲板
自衛艦は停泊が長いと、整備作業でガンガン錆打ちして、艦内も塗装し、ワックス掛けして完璧な状態に仕上げてましたが、民間船は停泊中=荷役なのでそこまで整備はできません。
航海中も少しできますが、潮をかぶったりするのでなかなかできる範囲は限られます。
仮バースや荷役待ちで港外アンカー中に、できますがせっかくの休養時間なので午前中に終わらせます。
やりじまいなので、やっつけ仕事する人が多いです。
錆打ちや磨きが甘かったり、ペンキの塗り残しもしょっしゅうです、養生しないので、はみ出しやポタポタこぼしても気にしていないので、まあまあカルチャーショックでした(笑)錆が出ないようにしたり、塗り残しがないようにと今でもそこは心がけていますが、少々こぼしたとしても、後で刷毛で伸ばせばいいやと、それよりもスピード重視で2年も経てば少々のことは気にならなくなりました(^^)/
本船は甲板部の人しかペンキ作業しないので、なかなか進みませんが色がグレーと白の2色なので、比較的楽です。
荷役設備
それぞれの船種により荷役設備を大きく変わりますので、最低限のことだけ早く覚えて、詳しいことは徐々に覚えていきましょう。
図面はたくさんありますが、未だにわからないことだらけです。
なにかの不具合が起こらないと、対処法は覚えられないと思います。
ドック中にメーカーの人に教わるのもいいと思います!
書類関係
船長や1航士のみで、2航士は記入するものはありますが、担当する書類はありません。
船全体にしても、自衛艦に比べると圧倒的に少ないです。
字を書くことやPC作業がなくなったので、久々にすると漢字がでてこなかったり、打ち間違えの回数に愕然とします(笑)
操練(訓練)
月に一回なにかの操練をするだけで、自衛艦のように毎日何項目やるとかはありません。
その他
ロープのアイ入れは、転職前にYouTubeなどで覚えておいてほうがいいと思います。
覚えてなくても実際にロープを使ってやらないとうまくなりません、ワッチ以外の時間に部屋でいくらでも練習できるので大丈夫です。
ホーサーの擦れあてをホーサーに入れ込みますが、一回教わったら簡単にできるので問題ありません。
まとめ
- 初めての出入港作業で覚えることがたくさんあるが、新しいことなので船乗りとしての自覚が芽生える。
- 仕事量は自衛官時代と比べて圧倒的に少なくなったので、十分な睡眠時間を確保できる
- 自分の時間がありすぎて、なにかしないといけないんじゃないかと不安になる
- 一人ワッチは大変だが、変針や減速時、灯台報告等を船長に報告しなくていいし、コーヒーを飲んだり、自分のリラックスできる状態で立直できる
- 仮バースや荷役待ちのアンカー中は、基本的には午前中のみ整備作業
- アンカーはワッチ対応なので、ツイてる時はガッツリ休める
- 担当書類や報告書を数件のみ
- 任務は安全に航行して、荷物を積んだり降ろしたりするのみ
私は自衛官在籍中のマークは「航海」でしたので、比較的に航海ワッチはスムーズにいけたかなと思います。
それでも、瀬戸内海を一人で航行するときは、今でもドキドキしながら走ります。
1分隊の方は、舵も見張りもでき、小型船舶も持っていますし、運航の資格も持っている方もいると思うので、海技免状も5、6級は難なく取得できるのではないでしょうか。
加えてオモテの作業も慣れてると思うので、自衛官から民間船に転職するには優位だと思います。
その他のマークの方も、乗船履歴があれば海技免状は頑張り次第で取得でき、あとは転職してから徐々に覚えていけばなんとでもなるので大丈夫です!(^^)!
いろいろ不安はあると思いますが、自衛隊よりもキツくありません、なんてったって一人部屋で寝れる時間は十分にありますからね(^^♪