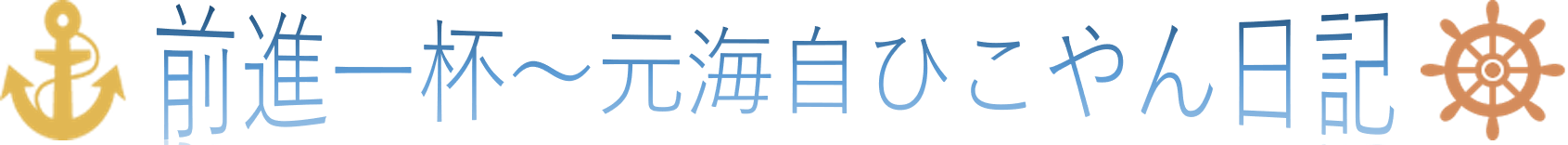内航船(ないこうせん)とは、日本の港と港の間を航行する船のことです。
日本の国内で物資を運ぶ「海の物流」を担っており、日本の経済活動を支える上で非常に重要な役割を果たしています。
外航船(外国の港にも寄港する船)とは異なり、内航船は国内のみを航行します。
内航船の種類
内航船の種類について、主なものをいくつかご紹介します。
内航船は、輸送する貨物の種類や、船の構造によって多岐にわたります。ここでは代表的な船種を挙げます。
ばら積み
ばら積み船は、日本の国内の港と港の間を航行し、貨物を袋や箱に詰めずに、そのまま船倉(ホールド)にばら積みして運ぶ船です。
主に石灰石、セメント、穀物、砂、砂利、石炭などの産業資材や食料を輸送します。日本の物流を支える重要な役割を担っており、内航貨物船の中でも特に数が多い船種です。
コンテナ船
コンテナ船(Container Ship)は、輸送する貨物をすべて規格化されたコンテナ(鉄製の箱)に詰めて運ぶ専用の貨物船です。この規格化されたコンテナの登場により、陸上(トラックや鉄道)と海上での貨物輸送が効率化され、世界の物流を大きく変えました。
路線バスのようにあらかじめルートとスケジュールを設定して、定期的に決まった港に寄港します。
タンカー
タンカー(Tanker)は、石油や化学薬品、液化天然ガス(LNG)など、液体や気体の貨物を専門に輸送するための船です。液体貨物をそのまま船内のタンクに入れて運ぶことから「油槽船」とも呼ばれます。
ガス運搬船
ガス運搬船は、液化天然ガス(LNG)や液化石油ガス(LPG)など、特殊な気体やガスを極低温・高圧の状態で輸送する、非常に専門性の高い船です。これらの船は、世界のエネルギー供給において不可欠な役割を担っています。
LNG船(液化天然ガス運搬船): 天然ガスを-162℃という極低温に冷やして液体にし、体積を約600分の1に圧縮して運びます。
LPG船(液化石油ガス運搬船): LPG(プロパンやブタンなど)を液化して運びます。
これらの船は、貨物の温度や圧力を厳密に管理するための特殊なタンクと設備を備えており、高度な安全技術と専門知識が求められます。
自動車専用船
自動車専用船(Pure Car Carrier: PCC または Pure Car and Truck Carrier: PCTC)は、その名の通り、自動車やトラック、バス、建設機械などを専門に運ぶ船です。船内は複数のデッキに分かれており、エレベーターやスロープを使って効率的に車両を積み下ろしできる構造になっています。
RORO船
RORO船(Roll-on/Roll-off Ship)は、自走可能な貨物(自動車、トラック、バス、建設機械など)を、そのまま船に乗り込み(Roll-on)、そのまま船から降りる(Roll-off)方式で輸送する船です。貨物の積み降ろしにクレーンを必要とせず、自走で積み降ろしを行います。、迅速な荷役作業が可能で、港での滞在時間を大幅に短縮できます。
長さ160~180mくらいあります。
セメント船
セメント船は、建設資材であるセメントを専門に運ぶ貨物船です。セメントをバラ積み(粉末状のまま積むこと)で輸送するため、専用の積み込み・荷下ろし設備を備えています。密閉されたタンクを使って輸送することで、セメントが湿気や水分で固まるのを防いでいます。
ガット船
ガット船は、船首に「ガットクレーン」と呼ばれる特殊なクレーンを装備した船で、自力で荷物の積み込みや積み下ろしができるのが最大の特徴です。
主に砂、砂利、石材、建設残土などの産業資材を輸送するために使われます。荷役設備がない港でも作業ができるため、災害時の緊急輸送や、港湾工事、防波堤建設などでも重要な役割を担っています。
フェリー
フェリーは、旅客と車両(自動車、バイク、トラックなど)を同時に運ぶ船舶です。短距離から長距離まで様々な航路で運航されており、人々の移動手段や物流の一端を担っています。旅客へのサービスを提供する客船としての側面と、貨物を運ぶ貨物船としての側面を併せ持っているのが大きな特徴です。
クルーズ船
クルーズ船は、旅客が船旅自体を楽しむことを目的とした豪華客船です。単なる移動手段としての船ではなく、船内にホテル、レストラン、劇場、プール、カジノ、スポーツ施設など、様々な娯楽施設を備えています。世界中の観光地を巡りながら、快適な船内生活を提供することが主な役割です。
飛鳥Ⅱ、飛鳥Ⅲ、にっぽん丸が代表的な船です。
船舶の規格
次に紹介する3つの型の内航船は、乗組員が少なく、1人ワッチ体制で運航します。
749t型には、司厨長がいる船もあります。
199トン型:499トン型と同様に、内航海運でよく見られる船型です。
499トン型:内航海運で最も一般的な船型の一つで、総トン数が499トン以下に制限されています。
749トン型:499トン型よりも大きな船舶で、積載量も多くなります。
| 199t型 | 499t型 | 749t型 | |
|---|---|---|---|
| 総トン数 | 199t | 499t | 749t |
| 積載トン数 | 約700t | 約1600t | 約2000t |
| 長さ | 約40~55m | 約60~75m | 約60~90m |
自動車専用船、RORO船、コンテナ船等は、これらより大きな船で、10数名乗組員がおり、職員(〇等航海士)と部員の2人ワッチ体制で司厨長がいます。
セメント船等もこれらより大きな船もたくさんあります。
船種ごとの比較表
| タンカー | コンテナ船 | 貨物船 (バルク船) | フェリー RORO船 | ガット船 | |
| 主な積荷 | ガソリン、灯油、原油などの液体危険物 | 雑貨、製品 (コンテナ入り) | 穀物、石炭、鉱石などのバラ積み貨物 | 旅客、自動車、 トラック | 砂、砂利、石材、建設残土など |
| 仕事内容 | 貨物(危険物)の積み降ろし、輸送、安全管理 | 貨物(コンテナ)の積み付け、荷役監督 | 貨物の積み降ろし、輸送 | 旅客・車両の誘導、接客サービス | 自船のクレーンによる荷役作業 |
| 乗組員 | 航海士、機関士、甲板員、機関員、専門訓練を受けた乗組員 | 航海士、機関士、甲板員、機関員など | 航海士、機関士、甲板員、機関員など | 航海士、機関士、甲板員、客室係など | 航海士、機関士、甲板員、機関員など |
| 勤務形態 | 航海が長く、高リスク・高スキルの業務 | スケジュールが厳格。港での滞在時間が短い | 荷役作業に時間がかかることが多い | 定期航路が多く、生活リズムが安定しやすい | 定期航路や特定の作業現場が多く、比較的勤務スケジュールが安定 |
| 給与 | 高い傾向にある | 船の大きさや航路により異なる | 船の大きさや運ぶ貨物により異なる | 航路や船の規模により異なる | クレーン操縦という専門スキルが求めら高くなる傾向にある |
| メリット | ・高収入が期待できる ・専門スキルが身につく | スケジュールが明確 | 比較的スケジュールに余裕がある | ・休暇が取りやすい ・生活リズムが安定しやすい | ・高収入が期待できる ・専門スキルが身につく |
| デメリット | ・危険物ゆえの高い緊張感 | タイトなスケジュールで作業負荷が高い | 荷役作業が長時間に及ぶ場合がある | 接客スキルが必要になる | ・陸上での重機(バックホウなど)の操作技術が求められることがある ・荷役作業が長時間にわたる場合がある |
終わりに
私が乗っている749t型には、AIS(船舶自動識別装置)や電子海図、オートパイロットがついており、バウスラスターもあります。
船の大きさにかかわらず装置の有無に違いがありますが、設備が整っている船が運航するのに助かります。
免状(船の免許証)や特殊無線の資格がないと、1人ワッチができません。
その場合は、大きな船に乗っていろいろ学び、乗船履歴をつけて免状を取得すれば、いろいろ道は広がります。
免状を持っていれば、民間船未経験の人でも、数名しか乗っていないワッチが1人体制に職員として船に乗れます。
最初の数か月は研修期間のように2人ワッチで、その後船長の判断で1人ワッチになりますので安心してください。
人数が多い船に乗ればマンツーマンで一つ一つ丁寧に基本から教えてもらうことができるので、船に慣れながらゆっくりと覚えていくことができます。
反対に乗組員の数が少なく1人ワッチの船は、マンツーマンというわけにはいかないので、作業を見て覚え、すぐにその配置につかないといけないので、かなり苦労します。理屈より体で覚える、という感じです。
結論でいいますと、免状等を持っている人は、内航船なら最初から職員として乗れるということです。
私もそうでしたが、どんな船種がいいのかわからなかったので、まず、1人ワッチか2人ワッチか、司厨長がいるのかいないのか、から選択していきました。
免状等を持っていない人に関しては、また別の記事で紹介させていただきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。